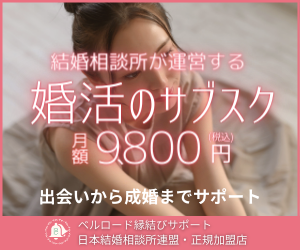19世紀
サラスヴァティはヴィーナという楽器を持ったヒンドゥー教の芸術と学問の神。
日本では弁財天。
招福・財運の神でもあります。
創造神・ブラフマーから生まれた絶世の美女。
ブラフマーはサラスヴァティを娘として生み、その美しさに魅了され、妻とします。
そして常に眺めていたいために4つの頭を持つようになったのだとか。
そんな女神サラスヴァティに注目です。
サラスヴァティの誕生と神格、ヒンドゥーの神々の独特な世界観、ご覧ください。
目次
サラスヴァティ、ブラフマーが生んだ娘で妻

ラヴィ・ヴァルマ作1896年
サラスヴァティとは
サラスヴァティ(Sarasvati)はヒンドゥー教の主要な女神様。
最高神(トリムールティ)の一柱、創造神・ブラフマーの神妃。
維持神・ヴィシュヌの配偶神・ラクシュミ、破壊神・シヴァの配偶神・パールヴァティーと共に、トリデーヴィー(トリムルティの配偶神の三女神、三位一体の主女神)の一柱
聖なる川・サラスヴァティー川の化身であり、「流れる川」から流れるもの全て、知識、学問、芸術、詩歌、音楽、浄化、言語、文化を司ります。
ブラフマナ(ヴェーダの経典)においては知識と同一視され、『ヴェーダの母』として崇められます。
日本の仏教伝来に際しては、金光明経を通じて中国から伝えられ、七福神の一柱・弁財天として信仰されるようになります。
サラスヴァティの神格

1900年代中期の宗教ポスター
サラスヴァティはインドの最も古い聖典「リグ・ヴェーダ」においては、聖なる川・サラスヴァティー川の化身。
サンスクリット語でサラスヴァティは「水(湖)を持つもの」を意味し、原初のアパス(水の神々)の一柱として、富、豊かさ、健康、治癒を授ける女神。
五穀豊穣と招福をもたらす女神として崇拝されます。
その後その名は「浄化する水」から「浄化するもの」「浄化する知識」へと進化し、知識、芸術、音楽、言語、そして、自己を浄化する創造性とそれを体現する概念へと発展してゆきます。
リグ・ヴェーダにおいてのサラスヴァティはディー(dhī)『霊感を受けた思考』を司る女神。
ディーは直感や知性をいいます
サラスヴァティに祈ればディーを授けてくれる神として信仰を集めます。
韻律・讃歌の女神ガーヤトリーと同一視され、ヴェーダ聖典や儀礼に用いられる祈祷の化身。
後のヴェーダ文献では言語の女神ヴァーチャと同一視。
次第にサラスヴァティーと川とのつながりは薄れ、言語、詩、音楽、文化を司る神として崇められるようになってゆきます。
そして中世のヒンズー教においてのサラスヴァティーは主に学問、芸術の女神であり、サンスクリット語の発明者として信仰されてゆきます。
容姿

バザールアート
サラスヴァティーは多くの絵画に4本の腕で描かれます。
4本の腕は夫ブラフマーの4つの頭を反映し、
- マナス(心、感覚)
- ブッディ(知性、推論)
- アハムカーラ(自意識、自我)
- チッタ(想像力、創造性)
を象徴しています。
4つの手にはそれぞれ、
- プスタカ(ヒンドゥー教の聖典) ー 普遍的、神性、永遠性、真の知識
- マーラ(数珠、花輪) ー 瞑想、内省、霊性の力
- 水差し ー ソーマ(知識に導く飲み物)の象徴。善と悪、清浄と不浄、本質と不本質を区別する浄化の力
- ヴィーナ(楽器) ー 調和を生み出す知識の表現を象徴。言葉や音楽で表現されるすべての感情
を持ちます。
ブラフマーは抽象、サラスヴァティは行動と現実を表しています。
多くの場合、サラスヴァティは、サットヴァ(善、清浄)の性質を表した純白の衣をまとい、光、知識、真実を象徴する白い蓮華に座る姿で描かれています。
足元には、白いガチョウ、白鳥、あるいは孔雀。
- ガチョウは、知恵の追求、善と悪、真実と虚偽、本質と外見、永遠と儚さを識別する能力の比喩とされるもの。
- 白鳥は、精神の完成、超越、解脱の象徴。
- 孔雀は、舞踏の祝典、自らの蛇毒を悟りの羽毛に変える能力を象徴しています
起源
サラスヴァティはヴェーダ宗教最古のリグ・ヴェーダ(紀元前1500年頃 - 紀元前1000年頃)に初めて登場します。
パンテオン(天界の神々)の中で、犠牲の女神・イーラと言葉の女神・バーラティと三位一体。
主に天上の水(アパス)と嵐の神々(マルト)と結び付けられ、雄牛のように吠え、大きく力強い洪水として、天から地上に降りてくると考えられていました。
サラスヴァティーの誕生
サラスヴァティーは「アヨーニジャ」。
これはサラスヴァティが子宮からの誕生ではなく、神として顕現したことを意味しています。
プラーナ文献には、サラスヴァティーの起源について様々な説が記されています。
主なものとして
◾️『ブラフマー・ヴァイヴァルタ・プラーナ』(愛と献身の女神ラーダー(クリシュナの妃)とクリシュナを中心に展開するヴィシュヌ派の文献)と『デーヴィ・バガヴァタ・プラーナ』(デヴィ(女神)崇拝者のためのマハープラーナ(文献))
サラスヴァティは、ムーラ・プラクリティ(原初の性質)。
または創造において異なる役割を果たすブラフマン(普遍原理)のシャクティ(力、エネルギー)で5つの顕現の1つ。
創造原初、ブラフマー神のアートマン(自我)は2つに分かれ、その右半分が男性原理となり、左半分がプラクリティ(基本原理)になります。
プラクリティ(基本原理)は
- ドゥルガー マヤ(幻想)とプラクリティ(自然の姿)の女神
- ラーダー クリシュナの正妃で献身の女神
- ラクシュミ ヴィシュヌの妃で幸運と富の女神、
- サラスヴァティ 神聖なサラスヴァティー川の化身、言語と知識の女神
- サヴィトリ ヴェーダの母の称号を持つガヤトリ・マントラ(聖なるマントラ)の擬人化
5つの形態になります。
◾️『ヴァーユ・プラーナ』(最古のブラーナの一つ)
ブラフマー神の怒りから半人半女の存在(プルシャ)が誕生。
この存在はさらに分裂を命じられ、男性の側面は11のルドラ(神々)に、女性の側面は白と黒の姿に分裂。
サラスヴァティは白い半分の顕現として誕生しています。
別の記述では、
ブラフマー神の瞑想の中で、宇宙の根源(ジャガディオニ)であるプラクリティを象徴するサラスヴァティーが、4つの口、4つの角、4つの目、4つの手、4つの歯を持つ神聖なガウ(牛)として出現しています。

マハデヴィ 18 世紀
◾️『ブラフマンダ・プラーナ』(宇宙開闢(かいびやく)最古の文献のひとつ)ラリトパキヤナの章
ヒンドゥー教の最高女神・トリプラ・スンダリが3つの宇宙の卵を創ります。
1つの卵からはサラスヴァティとシヴァ、他の卵の1つからはアンビカ(ヒンドゥー教の最高女神マハデーヴィー)とヴィシュヌ、もう1つからはスリ(ラクシュミ)とブラフマーが生まれました。
トリプラ・スンダリはその後、サラスヴァティーとブラフマー、アンビカとシヴァ、スリとヴィシュヌを結びつけ、神聖な配偶者をつくりました。
◾『️マツヤ・プラーナ』(人間の始祖・マヌが松屋の姿に化身したヴィシュヌ神に救われた物語を描いた最古のブラーナ聖典の一つ)
サラスヴァティはブラフマー神のマナサ・プトゥリ(心から生まれた娘)。
宇宙創造に際し、ブラフマー神は瞑想の中でその肉体を男性と女性の半分に分裂させます。
サラスヴァティは分裂された女性スヴァトマジャ(自らの自我が生んだ娘) として顕現します。
ブラフマーとサラスヴァティー

インド、カルナータカ州ハレビドゥのホイサレワラ寺院、12 世紀
サラスヴァティとブラフマーの物語は多くのブラーナ(聖典)で語られています。
『マツヤ・プラーナ』では
サラスヴァティーはブラフマーの体の左側から現れたと語っています。
サラスヴァティはブラフマーによって、当初娘として創造されました。
けれどにブラフマーはサラスヴァティの美しさに魅了され、娘ではなく、妻となるよう懇願します。
ブラフマーはサラスヴァティに見とれ、サラスヴァティーは見つめられる恥ずかしさから逃れる為にブラフマーの後ろにのかれようとします。
けれどその都度、ブラフマーに顔が生じ、ブラフマーは自らの前後左右の四方に顔を作り出してしまいます。
そして、天に逃れようとしたサラスヴァティを追う為に、更に5つ目の顔を作ります。(5つ目の顔は後にジヴァ神に切り落とされてしまいます)
こうしてブラフマーは4つの顔を持つ神となります。
ついに逃げられないと観念したサラスヴァティはブラフマーと結婚。ふたりの間には、スヴァヤンブヴァ・マヌが生まれます。
神妃ガーヤトリー
ブラフマーにはサラスヴァティ以外、ガーヤトリーという神妃がいます。
サラスヴァティは最上とされる女神、プライドも高く高慢でもあります。
ある時ブラフマーが神々を招き祭儀を行なった際、サラスヴァティは身支度のために出席が遅れます。
それを怒ったブラフマーが他の女神ガーヤトリーを妃に迎えて祭儀を行います。
サラスヴァティは激怒し、ブラフマーには祭儀は1年に1度しかできないという呪いをかけます。
ガーヤトリーは、サラスヴァティが第一の妃であることを認めるという約束を受けてその存在を認められます。
ヴィシュヌとサラスヴァティ

シカゴ美術館
けれど他説、サラスヴァティはヴィシュヌ神の妃のひとりとして記されています。
『デーヴィ・バガヴァタ・プラーナ』では、
サラスヴァティーは富と幸運の女神・ラクシュミーとガンジス川の擬人化で浄化と許しの女神・ガンガーと共にヴィシュヌの3柱の妻の1柱。
ある時ガンガーとの間に争いが怒り、ラクシュミーが仲裁に入ります。
サラスヴァティはラクシュミーを呪い、トゥラシ(植物)として生まれさせ、ガンガーはサラスヴァティーを川と化す呪いをかけ、サラスヴァティーも罪人はガンガーの水で罪を清めるという呪いをかけます。
ヴィシュヌは争いの原因となったサラスヴァティに、一つはヴィシュヌに添い、一つは地上の川となり、そしてもうひとつにブラフマーの配偶者となるという三つの姿を持つよう命じます。
弁財天になったサラスヴァティー

法橋狩野常真作 十七世紀
サラスヴァティは日本に仏教が中国から伝来した際、仏教聖典のひとつ「金光明経」において国を守る諸天善神の1柱、“弁財天(弁才天)”として伝えられています。
弁財天は学問・智慧・弁舌・音楽などの芸術全般を司る神として以外にも、財運や招福、長寿を授けるとされ、七福神の中のただひとりの女神でもあります。
また弁財天(サラスヴァティー)は、神仏習合思想のひとつ「本地垂迹(ほんじすいじゃく)」(日本の神々は仏や菩薩が化身した権現(であるという思想)においては、市杵嶋姫命(いちきしまひめ)(アマテラスとスサノオが誓約を行った際に霧から生まれた水の神)と同一視されます。
サラスヴァティ、弁財天としてもご多忙
「ペルソナ5」でのサラスヴァティは女教皇のペルソナ。ブラフマー神の妻でありインド神話の学問と芸術の女神。後に仏教に入り弁財天となります。
ーーーーーーーーーー
「モンスターストライク」の弁財天は『激獣神祭』のイベントで登場した光属性の女性型キャラ。音楽をこよなく愛するアイドル女神さま。
ーーーーーーーーーーー
「聖☆おにいさん」の弁才天はジャンル関係なし、音楽ならなんでもOK、性格もロックな女神様。
ーーーーーーーーーー
サラスヴァティ まとめ

マイソール絵画19 世紀 ドゥルガーダ・クリシュナッパ-国立近代美術館
ヒンドゥー教の神々は乳海から生まれたり、神の体の一部から生まれたり、娘が妻になったり、決別、再婚、重婚も全然アリで、複雑怪奇。
まあ、神が宇宙や自然、力や概念の権化なのですから、それも自然なことなのかもしれません。
小さな尺度でしかみられない人間如きの理解の域を超えた世界観にただただオドロキの一言です💦