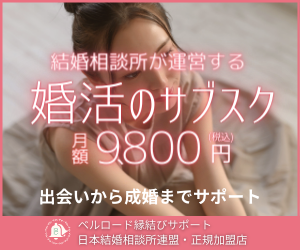太田聴雨作
牡丹灯籠は「四谷怪談」「『皿屋敷』と並ぶ日本三大怪談の1つ。
お露という名の幽霊が「カラン、コロン」と下駄の音を響かせながら、恋しい男の元に通います。
元は落語の人情噺であったとされる『牡丹灯籠』
それがなぜ怪談になったの?
その成立やあらすじは
牡丹灯籠 、怪談になった恋する女の情念

豊原国周 作
牡丹灯籠とは
『牡丹灯籠』(ぼたん どうろう)、または『怪談牡丹燈籠』(かいだん ぼたん どうろう)は「四谷怪談」、「皿屋敷」と並ぶ日本三大怪談の1つ。
元は明治の落語家・三遊亭圓朝創作の怪談噺として生まれます。
圓朝が25歳の時の作品。
圓朝は(江戸前期の僧侶であり作家)浅井了意による怪奇物語集『御伽婢子』や深川に伝わる米問屋の怪談、牛込の旗本で起こった実話などから着想を得て創作。
明治17年(1884年)、速記本が刊行されています。
その中の『御伽婢子』は、中国の怪奇小説集『剪灯新話』の中の一作『牡丹燈記』を翻案したもの。
その『牡丹燈記』は恋しい男性と逢瀬を重ねた若い女の幽霊が、恋人に幽霊と知られ、幽霊封じで拒んだ男性を恨んで殺すという内容のもの。
圓朝はこの幽霊話に多くの事件と登場人物を加え、それらが複雑に絡み合う長編ドラマを作り上げています。
この物語を、明治から昭和にかけて活躍した六代目三遊亭圓生は
- 「お露新三郎」 お露と新三郎の出会い
- 「お札はがし」 お露の亡魂が新三郎宅に通い、幽霊封じに合う
- 「栗橋宿/お峰殺し」 「関口屋」を開業した伴蔵は酌婦のお国と恋仲になり、それを咎めた妻のお峰を殺害
- 「関口屋・強請」 死んだお峰に祟られた伴蔵はお国の素性を知り、商いを引き払い江戸に帰る
に分類。
一般に「牡丹灯籠」として知られる物語は、本来の物語から前半の内容を抜粋した短編。
明治25年(1892年)には、3代目河竹新七により歌舞伎『怪異談牡丹燈籠』(かいだん ぼたん どうろう)として、5代目尾上菊五郎主演で上演されています。
あらすじ

世界文庫・牡丹灯籠挿絵
江戸・根津に住まう浪人の萩原新三郎は二十一歳の美男。
けれど、家にこもって本ばかり読んでいる内気な性格。
ある日、知人の誘いで旗本・飯島平左衛門の別荘を訪れます。
そこで十七の美しい娘、お露と出会います。
一目でふたりは互いに激しく惹かれ合います。
帰り際、お露は「また来てくださらなければ私は死んでしまいます」と新三郎に告げ、新三郎はこの言葉をひとときも忘れられずにいました。
その後、新三郎はお露に会いたくてたまらないものの、ひとりで逢いに行く勇気がないまま数ヶ月が経ってしまいます。
そんなある日、お露を紹介した知人が新三郎を訪れます。
そしてお露が亡くなったことを告げます。
「お露さんは会えない新三郎に焦がれ、ついに死んでしまった。女中のお米さんも看病疲れで後を追うように亡くなった」とのこと。
それからの新三郎はお露の俗名を仏壇にそなえ、念仏を唱え続ける日々をおくります。
そうして暮らす盆の十三日の夜、ふと気付くと『カラン、コロン』という下駄の音が響いてきます。
そうして牡丹芍薬の灯籠で夜道を照らすお米の後に、愛おしいお露が新三郎宅を訪れます。
新三郎は二人を家に迎え入れ、二人は新三郎のもとで一夜を過ごします。
次の晩もその次も、お露と新三郎の逢瀬は続きます。
ある日、新三郎の孫店に住む伴蔵は、毎夜新三郎のもとに通ってくる女がいることを不審に思い、中の様子をうかがいました。
すると、そこには骨と皮ばかりで腰から下がない女が新三郎の首へかじりついています。
驚いた伴蔵は家に逃げ帰ります。
翌朝、伴蔵は新三郎も交流のある易者を訪れます。
易者は「幽霊と契りを結べば必ず死ぬ」と告げ、易者と伴蔵は新三郎のもとを訪れます。
新三郎を見た易者は「二十日を待たずして死ぬ相が出ている」と新三郎に告げます。
俄かには信じられない新三郎は三崎村に住んでいるというお露の家を探しに行きます。
けれどその家はみあたらず、あきらめて帰ろうとお寺の境内を通ると、お堂の前に牡丹の灯籠が置いてある新墓をみつけます。
誰の墓かと寺の僧に聞くと、飯島平左衛門の娘と女中の墓と答えられます。
お露の正体が幽霊であることを知った新三郎は、お露を埋葬しているお寺の和尚から幽霊除けのお札をもらい、死霊除けの海音如来像を拝借して帰ります。
そうして、家の回りに隙間なくお札を貼り、海音如来を抱いて、家に籠ってお経を一心に唱えます。
八つの鐘が響くころ、いつものように「カランコロン」と駒下駄の音が響いてきます。、
いつものように恋しい新三郎のもとに来たお露。
けれど張り巡らされたお札のために家に入れません。
中からは新三郎の読経の声も聞こえてきます。
あきらめきれないお露。
そこでお米は伴蔵にお札をはがしてくれるように頼みに行きます。
はじめは断り続けていた伴蔵ですが、女房のおみねに「百両もらってお札をはがしておやり」とそそのかされます。
おみねは家に籠りっきりの新三郎を不潔だと言って行水させ、その隙に海音如来を粘土の不動像に入れ替えます。
その晩、二人の幽霊が来ると、伴蔵はお札を全部はがしてしまいます。
お露はすぅ~と、家の中に入ってゆきます。
明け方、伴蔵は新三郎の家に様子を見に行きます。
戸を叩いても返事はなく、家の中はし静まりかえっています。
伴蔵は恐る恐る家の中に入って行きます。
そうして、その首に髑髏がかじりつき、物凄い苦悶の表情で息絶えている新三郎を見つけます。
牡丹灯籠 まとめ

月岡芳年作
私は女なんで、男心というものはよくわかりません。
けど、私がもし新三郎のような世渡り下手で内気な男だったら、狂おしいほどに愛おしい相手なら、たとえ幽霊でもノープロブレム。
目の前にいるのはまんまその人なんで、霊界でもどこででも添い遂げようと思うだろうなっと思いますが。。。
まあ、いろんな女がいるように、いろんな男もいるんで、こんなこともあるのかなぁ〜